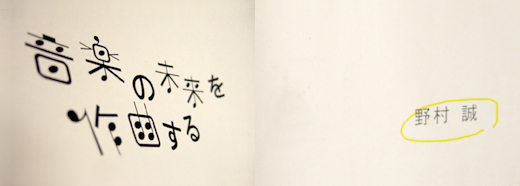
1 「私たちの音楽」を楽譜化する
ぼくはガムラングループ「マルガサリ」とのコラボレーションを通して、「私の音楽」から「私たちの音楽」への模索を続けた。中川真さんからの依頼は、楽譜を使わないで作曲することだった。楽譜に固定しないことで、「桃太郎」は常に変化をし続け、演奏者が演奏するたびに、微妙に改変が加えられ変化していく音楽になっていった。
同じように、イギリスの作曲家ヒュー・ナンキヴェル(Hugh Nankivell)と共同で行ったプロジェクト「ホエールトーン・オペラ」も、「私たちの作品」を作り上げる試みだった。全4幕、40曲以上にのぼる楽曲は、全てワークショップを経て作られたもので、基本的には楽譜に書かずに作曲された。
ワークショップは、音楽の経験・能力を問わずに広く公募した。日本で行ったワークショップでは、和太鼓奏者、学校教員、ピアノ教師、アマチュア劇団員、大学生など約15名が参加。イギリスでは、知的障害者の劇団の俳優、音大生、アマチュア音楽家などが参加。日本でもイギリスでも、毎回プロの音楽家4名がゲストとして加わった。できあがった作品は必然的に、専門家から初心者まで、様々な演奏能力の人が共存できる作品になっていた。
しかし、こうした共同作曲作品は、誰にでも開かれている作品であるはずなのに、作曲に関わった人でしか演奏できないという難点がある。作曲のプロセスを体験している人にとっては、自分の身体に音楽が入ってしまえば、楽譜などなく自然にその楽曲を演奏できるし、その音楽を成立させている漠然としたルールも肌で理解できる。一方、作曲のプロセスを体験していない人にとっては、どういう仕組みで演奏しているのか、何が決まっていて、何が演奏者の自由なのか、さっぱり分からず困惑する。そうすると、開かれた作品を目指した「私たちの作品」が、非常に排他的な音楽にもなってしまいかねない。
また、人の個性に着目して生まれてきた音楽は、その人がいないと成立しない。別の人がそのパートを真似してやっても、曲の持ち味が出なかったりする。結果、開かれた作品だったはずの音楽が、あるコミュニティに限定された閉じた音楽になってしまう。
こうした問題に答えるべく、「ホエールトーン・オペラ」は、楽譜集を作って出版することにした。楽譜の序文の中で、楽譜について以下のように書いた。「ホエールトーン・オペラを創っているとき、私達は、ほとんど楽譜を書かなかった。ほとんどは記憶して演奏した。しかし、全幕上演をするにあたり、ヒューとノムラは、記譜することで合意した。それには、以下のような理由がある。」
そして、以下の5つの理由をあげた。
・未来に他の人が上演できる。多くの美しい歌や楽曲、興味深い構造などが忘れ去られず残せる。
・演奏者が音楽を短時間で効果的に習得できる。
・創作に関わった人々全員が共有するスコアを作りたかった。
・この種のスコアはあまりない。
・再演する度に変形されていくので、現時点での形をとどめておこうと思った。
つまり、当初のアイディアとしては、ワークショップの記録としての楽譜集としての意図が大きかった。ところが、実際に楽譜を書いていくにつれて、予想外な展開が始まるのだ。
2 作曲を推奨する楽譜
野村誠+ヒュー・ナンキヴェル「Whaletone Opera ~ 21st century musical journey」(2007、えずこホール)には、創作ノートと上演のための注意事項、そして全4幕の楽譜を書いた。ぼくは、この楽譜を作るときは、それぞれの楽曲を再現できる楽譜にしようと考えていた。ところが、ヒューと楽譜化する中で、楽譜の根源的な問題を意識し始めることになる。
「ホエールトーン・オペラ」は、せっかく開かれた作品として、「私たちの音楽」として作ってきたのに、ワークショップで作曲した「結果」として楽譜に固定してしまうと、開かれていた作品が、手を加えられない作品になってしまう。ジャズの楽譜だったら、メロディーとコードネームだけが固定されていて、アドリブや細かいやりとりは演奏の度ごとに変わっていく。固定されている部分と、演奏者の自由に任される部分がある。「ホエールトーン・オペラ」は、それよりももっと自由度の高い楽譜になるべくだ。気がつくと、楽曲を記録するというよりも、作曲を推奨する楽譜が生まれてきていた。
例えば、第1幕2曲目の「寒いのイヤ」では、オリジナルの歌の楽譜を載せた上で、「この楽譜と違うヴァージョンの歌を新たに作ってもいいが、『寒いのイヤ』の部分だけは原曲通りにしてください」と書いた。こうすれば、再演する度に、新たな歌が作詞・作曲される可能性が出てくるし、もとのワークショップで生まれた音楽のスピリットも残る。
また、第1幕5曲目の「バナナケーキレシピ」では、「新しいヴァージョンを作ってもよいし、オリジナルに従ってもよい。」と書いてある上で、原曲の楽譜と同時に、新しい楽曲を作るための手順が記されている。「バナナケーキレシピ」は、作曲のレシピでもあるのだ。
第1幕6曲目の「ケーキをふるまう音楽」では、「バナナケーキを観客にふるまうための音楽を、新たに作ってもよいし、第1幕初演時に演奏した以下のボサノヴァ曲を演奏してもよい。新しい曲を作る場合は、ホエールトーンスケールを使った曲を作ること。」と書いた。
また、第2幕10曲目の「フィナーレ(ドラミング)」では、「たいこの曲を作ります。既存のリズム(サンバ、ドラムンベースなど)を使ってもいいし、そうでなく好き勝手にやってもいいです。たいこ以外のパーカッション、管楽器なども使ってもいいです。アレンジをけっこうしてもいいし、しなくてもいいです。楽しんでください。」と書いた。
できあがった楽譜は、多くの楽曲で再作曲を推奨する表現を含むものになった。できあがった楽曲を楽譜として固定することと、それを参考にまた新たに作り変えることを推奨する。音楽を楽譜として固定することと、音楽を楽譜から解放すること、矛盾した二つをどうやって同時に実現するか、試行錯誤して楽譜を作り上げた。こういう楽譜があり得るのだ、というのが、ぼくにとっては大きな発見だった。作曲家の坂野嘉彦さんは、「ホエールトーン・オペラ」の楽譜を見て、「多くの作曲家が『交響曲』というスタイルで作品を書いているように、多くの作曲家が『ホエールトーン・オペラ』というスタイルで新しい作品を書くことが可能だと思う」と語った。作曲家が完全に楽譜に記譜した「ホエールトーン・オペラ」もあり得れば、子どもがワークショップで共同作曲する楽譜を使わない「ホエールトーン・オペラ」もあり得る。ワークショップで再演しながら、作品を開いていく楽譜の書き方を現在も模索中だ。そして、ぼくが想像もしないような「ホエールトーン・オペラ」に、いずれ遭遇することだろう。できるだけ色々な人に再演して欲しいので、「ホエールトーン・オペラ」の楽譜を、国内外各地の図書館などに寄贈して、閲覧可能な状況を作っていこうとしている。
3 かたい楽譜とやわらかい楽譜
「ホエールトーン・オペラ」の楽譜は、一体、何を記録しているのか?「ホエールトーン・オペラ」の楽譜で、ぼくとヒューは何を追求しているのだろう?この楽譜は、大きく分けて以下の3種類のことを記録していることに気づく。
(1)作曲の方法/作曲のプロセス
(2)作曲の結果
(3)改訂の可能性
(1)の「作曲の方法」とは、例えば、「ホエールトーン・スケール」を使ってメロディーを作るとか、書道をして、その曲線を図形楽譜とみなしてメロディーを創作するなどを指す。(2)の「作曲の結果」というのは、ワークショップで作曲された曲を再現するために、曲の構成、楽器の編成、メロディーライン、リズム、強弱、アーティキュレーション、ニュアンスなどを可能な限り厳密に書いたものを指す。または、その音楽を成立させる演奏上のルールを、できるだけ厳密に書いたものを指す。(3)の「改訂の可能性」は、(2)の楽譜を踏まえつつ、条件が揃わない時、または修正を加えたい時に、どう対応すべきかについての指示を指す。
従来、楽譜と呼ばれる物のほとんどは、(2)(=作曲の結果)のみを記しているはずだ。それは、次の2つの考え方によって成り立っていると思う。つまり、
A)作曲とは完成するものである
B)楽譜とは完成した楽曲を記録するものである
という二つの考え方だ。こうした考え方を前提にした楽譜を、「かたい楽譜」と呼んでみる。「かたい楽譜」で記された音楽は、それ以上、修正されることがなく、形をそのままに留めることができる。10年前にイギリスで作曲された音楽を、10年後のタイで演奏しても、10年前のイギリスと同じ音楽が再現されるようにできている。一方、
A’)作曲とは完成しないものである
B’)楽譜とは未完成の楽曲に参加するために存在するものである
という考えに立つと、楽譜の意味合いが全く違ってくる。こうした楽譜を、「やわらかい楽譜」と呼んでみることにする。「やわらかい楽譜」の音楽は、形が変化することを前提とした楽譜である。10年前にイギリスで作曲された音楽を、10年後のタイで演奏する場合、10年前のイギリスの音楽と無関係ではないが、再現ではなく、作曲上の何らかの展開が起こるはずである。
「ホエールトーン・オペラ」の楽譜は、基本的に「やわらかい楽譜」を目指している。「かたい楽譜」にとっては、(2)(=作曲の結果)こそが重要なのだが、「やわらかい楽譜」にとっては、(2)はあくまで現時点での一つの可能性を示しただけに過ぎない。だから、(2)だけを記すのではなく、(1)〜(3)までの全てを記載していく方が、「やわらかい楽譜」として、より有効になる。「やわらかい楽譜」に取り組む人が、共同作曲のプロセスに関わった人と同じ立場に立つためには、この3つの要素全てを知ることが必要だからだ。そうすることで、多くの人が未完成な共同作曲に、途中からでも参加できるようになる。
現代を生きる作曲家として、ぼくの大きなテーマは「やわらかい楽譜」の書き方を確立していくことにある。
4 謎を記録する
2009年ヒュー・ナンキヴェルと開始した新プロジェクト「キーボード・コレオグラフィー・コレクション(KCC)」は、ぼくにとって「やわらかい楽譜」を追求する新プロジェクトでもあった。「KCC」は、保育園児のピアノ演奏をビデオ撮影し、ピアノの演奏を振付として記述していくプロジェクトだ。第1回のプロジェクトは、2009年1月に、深谷保育園ゾウ組で1時間強のセッション3回が撮影され、その映像をもとに、野村誠、Hugh Nankivell、佐久間新(ジャワ舞踊家)の3人が分析し、「やわらかい楽譜」として楽譜化し、その楽譜をもとに、えずこホールでワークショップを行った。
分析を行っている時点では、ぼく自身「やわらかい楽譜」という概念を思いついていなかったし、(1)作曲の方法/作曲のプロセス、(2)作曲の結果、(3)改訂の可能性、という3つの要素を楽譜化することにも、自覚的ではなかった。しかしぼくたちは無意識に、映像から楽譜化するとき、次の3つの要素に分類をしていた。つまり、
a) Techniques
b) Approaches
c) Questions
だ。
Techniquesにあげたものは、まさに(2)(=作曲の結果)にあたるもので、実際に映像上で行われたピアノ演奏技巧を、そのまま記述したものである。例えば、「一本指で真上からゆっくり鍵盤に向かって下ろして、鍵盤に触りそうなところで、熟考して、一音をやさしく弾く」、「猫背になって鍵盤のすぐそばに目を近づけて演奏した後、肘をまっすぐ、背筋もまっすぐ、両手を左右に開いて演奏」など、具体的に行われた結果を記述する。
一方、Approachesは、まさしく(1)(=作曲の方法/プロセス)に対応するもので、例えば、「ピアノとスネアドラムと卓上木琴の3つともを同じ演奏法で演奏してみる」、「椅子の上に紙を置き、色ペンやクレヨンなどを使って、音楽または振付のためのスコアを、100秒で描く」、「譜面台に楽譜と思えないようなものを置いて演奏する」など、実際の作曲結果にいたるプロセス/方法を記載している。
こういう意味で、KCCのTechniquesとApproachesは、「やわらかい楽譜」の(1)、(2)の条件を見事に満たしている。また、KCCの序文の中で(3)についても言及している。ところが、KCCでは、「やわらかい楽譜」の(1)〜(3)にはなかった新要素、Questionsが登場した。これは、KCCを行う過程で生まれてきた疑問点で、例えば、「同時に何人でピアノを平和に演奏できるか?」、「非常に短い制限時間を設けることで、創造性は増すのか? それは、大人と子どもで違うのか?」、「全ての作曲家は振付家か? 全ての振付家は作曲家か?」などである。「やわらかい楽譜」をより未完成な作曲に参加するための覚え書きとして提示する上で、この「疑問点」を列記するやり方は、非常に有効だと思う。今後、「やわらかい楽譜」を書く上で、
(1)作曲の方法/作曲のプロセス
(2)作曲の結果
(3)今後の可能性
(4)浮上した謎
の4つを記録していくことで、成立していくのではないか。
5 誤解の生じる楽譜
KCCでは、(2)(=作曲の結果)として、映像を見て、子どもたちの様々な演奏テクニックを記述した時、大きく分けて二つの記述の仕方があった。
A) 実際の演奏法が再現できるように、テクニックを解説
B) 実際の演奏法とは違った解釈(誤解)が生じるように、テクニックを解説
例えば、「げんこつで3回、力強く」という指示の場合、「げんこつ」と「力強い」以外の点では、再現性がない。例えば、音域は高音域なのか、低音域なのか? リズムはどんなリズムなのか? 両手なのか、片手なのか、両手で交互に弾くのか?など、様々な不明瞭な部分がある。
A)の立場は、こうした不明瞭な部分を少しでも少なくする。その結果、演奏者が楽譜の通りに演奏すれば、作曲者の意図した音に限りなく近い音楽が再現できる。例えば、ブライアン・ファーニホウの楽譜は、かなり細部にわたって演奏の仕方を記述している。
そこで、KCCのワークショップで、もとの映像の演奏に限りなく近づけるように、進めてみた。ところが、これを続けていくと、映像の演奏にどんどん近づいていくのだが、そこから何も展開がない。また、子どもの即興演奏は面白いのだが、忠実に再現することに、それほど必然性を感じないし、払った労力が報われない気がしてきた。
そこで、ぼくらは B)の立場に、次第に移行していった。映像の演奏をもとに、誤解が生じるような文章の記述の仕方を追求した。例えば、子どもの即興演奏の映像を見ていたら、椅子の上で、少しだけ前後に揺れた動きがあった。この動きをもとに、以下のような楽譜を書いた。
「ピアノ椅子に座って、足を浮かせて、振り子やシーソーやブランコのように、前後に揺れながら、演奏する。前に来た時は鍵盤に触るが、後ろにふられる時は、鍵盤から手を離す。これを続ける。」
ワークショップ参加者に、子どもの映像を見ずに、この楽譜を演奏してもらった。すると、もとの映像では想像もしなかった多様な表現が、次々に生まれてきたのだ。ぼくらはこれが面白くて、どんどん誤解が生じるような表現で、子どもの即興演奏を楽譜化していった。
「ひやかす聴衆。手を握り、身をくねらす。自分の思考を口から手に込める。椅子に座って。指令を解読しようとする。ためらう足。決意して始めの音を探す。同意を求めて周りを見渡す。誰かが背後から近づいてくる。そして何かをささやく。はっきりしない音を出す。世界の見え方が変わる。楽譜のにおいをかぎながら、楽譜に尋ねる。世界に認められる一音を鳴らす。」
こうした書き方をすることによって、「作曲の結果」自体も、無限の解釈が可能な楽譜になっていく。だから、クリエイティブな誤解が生まれるように楽譜を書くこと、詳細に記述しながら、無限な解釈が可能な楽譜を書くことこそ、音楽の未来を作曲することになる、と思う。
〔まとめ〕
楽譜には、完成した作品を再現するための「かたい楽譜」と、不完全な作品に参加していくための「やわらかい楽譜」がある。「やわらかい楽譜」は、
(1)作曲の方法/作曲のプロセス
(2)作曲の結果
(3)今後の可能性
(4)浮上した謎
から構成すると効果的で、特に、(2)の「作曲の結果」を多義的な解釈が可能な形に記述すると、作品がより開かれていく。
(次回へ続く)
2009.2.3 update
