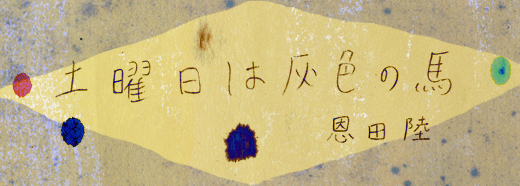
現在、私が所有している内田善美の漫画は四冊しかない。
ぶ〜けコミックスの『ひぐらしの森』と、四六判『星の時計のLiddell』1〜3巻だ。今となってはどうしようもないが、なぜ彼女の代表作と言われるであろう『空の色ににている』や『かすみ草にゆれる汽車』、りぼんマスコットコミックスで持っていたりぼん&りぼんデラックス掲載の全短編『星くず色の船』と『秋のおわりのピアニシモ』を手放してしまったのか、かつての自分を罵りたい気持ちでいっぱいである。
しかし、同時に、それらの漫画を処分する時に、自分がいったん少女漫画を卒業するのだ、という意識があったこともよく覚えているのだ。なにしろ、この時、私は小学校に上がるか上がらないかに初めて買ってからこのかた、えんえん集めていた少女漫画のコミックス数百冊を全て処分したのである。そのすべての中から内田善美の作品を残したのが、私にとっての最後の少女漫画家、と彼女を呼ぶゆえんだ。そして、内田善美の漫画のなかで最も好きな『ひぐらしの森』を選んだのは、いわば記念品のような扱いであった。
美しく気まぐれな女王様タイプの少女と、優等生タイプの地味な少女が不器用に友情をはぐくむ、ひと夏の物語。山の中の別荘地。美しい親戚の少年たち。もちろん、私の『蛇行する川のほとり』はこの物語から影響を受けている。最も私の好きなタイプの、少女漫画らしい一編だ。
かつてはみんなの部屋に飾ってあったペナントのようなもの。めったに開いてみることはないが、我が青春時代の記念として飾っておくにふさわしいタイトルであった。
『星の時計の〜』の場合、ポジション的に『ひぐらしの森』とはちょっと異なる。この本を買ったのはいったん少女漫画を「卒業」してしばらく経ってからだったし、少女漫画としてではなく、自分の好きなジャンルの翻訳小説のような位置づけだったのだ。それこそ、もう改めて読まないかもしれないけれど、本棚には並べておきたいサリンジャーやブラッドベリの小説を取っておくような感じだったのである。
内田善美がりぼん&りぼんデラックス時代に発表した漫画はほぼ全部覚えている。
デビュー作は「なみの障害物レース」で、りぼん本誌の登場だった。足の悪い女の子のどちらかといえば「感動もの」系の話だったが、それよりも一年くらいあとに発表された「七月の城」のほうが強く印象に残っている。アメリカ建国二百年記念日の話で、主人公の女の子が「ゴシックもなければルネッサンスもない」と呟き、ヨーロッパコンプレックスを友人たちに笑われる、という場面をくっきり覚えているのだ。なにしろ、少女漫画の中の外国は「西洋」とひとくくりにされていたのに、アメリカがヨーロッパに対してコンプレックスを持っている、なんていうのは初めて目にする概念だったのだ。
私の記憶が確かならば、いっとき内田善美は大矢ちきのアシスタントだった、という説がまことしやかに囁かれていた。
それは、絵を見れば一目瞭然だった。華麗で緻密で西欧的な、確固たる線の絵。今見れば全然違うのだけれど、当時はこういうタッチの漫画家は珍しかったので、同じ系列と思ってしまったのかもしれない。 しかし、大矢ちきには庶民に訴える少女漫画ちっくな「サビ」のようなものがあったが、内田善美の漫画にはよくも悪くも読者に対する「媚び」がなかった。内田はものすごいテクニシャンではあったが、その技巧派ぶりが逆にイラスト的で人物が動いていない、という批判を呼び 寄せたようである。
しかし、それこそが逆に後年ぶ〜けで花開く、独特の硬質な世界を構成するための支柱だったのだ。
後年の代表作、私の手元にある『星の時計のLiddell』を見ても、「人物が動いていない」という欠点は解消されていない。バスケットボールの場面を見ても、音がなくストップモーションのように見えてしまう。にもかかわらず、ここまで来ると、画面が大きく見開きで使われるようになったこともあり、その欠点すらもが、完成されたギリシャ彫刻のように見えてくるのだから不思議だ。むしろ、かえって彼女の硬質かつ静謐な世界がゆるぎない精度で迫ってくる。
その技術力は、異世界ものを描く時に大いに発揮された。「パンプキン・パンプキン」や「銀河その星狩り」などの異世界ファンタジーのデザインの完成度は今にしても凄かったと思うし、そういう意味では、学園ものを描いていても、内田善美が描くものは常に異世界だった。比較的普通の恋愛ものと思われる「秋のおわりのピアニシモ」にしても、合唱部の女の子とバスケットボール部の男の子の通う高校はリアルであってリアルでなかった。少女はあくまでも楚々として透明感があり、運動部のキャプテンである少年は、物静かで老成した知性すら漂わせている。学校の外には静かな野原が広がっていて、二人のデートはそこで本を読むことである。草のいっぽんいっぽんに手が触れるように感じ、学生服の襟の固さや少女の髪の感触すら感じられるような、質感のある描写。そうした細部の描写がリアルであるからこそ、逆に造り上げられた異世界、という感覚が強まってしまうのだ。
過去の古い日本を描いても、異国を描いても、そこにあるのは内田善美の造る確固たる「別の、もうひとつの世界」になってしまう。内田善美の漫画としてのリアルさが、少女漫画の虚構をある種つきつめた完成形に導いたように思えてならない。その点でも、やはり私にとって彼女は「最後の少女漫画家」なのだ。
内田善美の漫画の読後感は、一種独特だ。漫画というよりは、詩のようだ。それも、映像詩。タルコフスキーの映画や、NHKで『四季・ユートピアノ』など、実験的な作品を撮っていた佐々木昭一郎なんかの映像を観た時の印象に似ている。あるいは、ライアル・ワトソンの文章。
ライアル・ワトソンは、今ではやや「トンデモ系」に入れられているような気がするが、一世を風靡した科学者(? 専門分野はなんだったっけ)であり、『ネオフィリア』とか、『風の博物誌』とか感心しながら読んだ記憶がある。その科学とスピリチュアルの越境かげんが特に『星の時計のLiddell』に似ているのだ。ただし、内田善美の視線は、ロマンチストで万物に対する愛に溢れたワトソンよりも、遙かに冷徹で距離感がある。
『星の時計のLiddell』は、彼女のすべてが注ぎ込まれた文字通りの大作であり代表作であることは間違いないが、第一巻の帯は「少女漫画に新たな神話が誕生」、第二巻の帯は「人間の深層心理に迫る大型ミステリー」、第三巻の帯は「内田ロマンの神髄がここに 完結!」とある。確かに、この漫画の内容を説明するのはむつかしい。編集者が帯の惹句に苦労したことが窺える。
なにしろ、書き出しの一行は、「幽霊になった男の話をしよう」という、およそ少女漫画らしからぬものだし、テーマは、「地球上唯一の異質でいびつな生命体である人類はこれからどこに向かうのか」という、更に少女漫画らしからぬ哲学的なものなのである。
久々に読み返してみたが、実に不思議な話だ。主軸になっているストーリーは、アンドレ・モーロワの「夢の家」という幻想短編に似ている。夜ごと夢に出てくる家を探して辿り着いたら、主人は幽霊屋敷だと怖がって引っ越したあと。幽霊屋敷なんて、そんな馬鹿な、と笑うと、「幽霊はあなただった」と管理人が答える、という話。
『星の時計のLiddell』のほうは、シカゴが舞台。ヒュー・V・バイダーベックという青年が、繰り返し見る夢の中で出てくる家とそこに棲む少女を捜すという話だ。
実は、ヒューは睡眠時無呼吸症候群であり、呼吸せず心臓も止まっている状態の時は必ず同じ夢を見ている。それは子供の頃から見ていたもので、夢といっても、白昼も突然金木犀の香りを嗅いだり、声が聞こえてきたりする。夢に惹かれていた彼は、ある日夢の中の少女から助けを求められたため、この家を探す決心をするのである。
と、あらすじだけ書くと「?」という感じだが、話のほとんどを占めるのはヒューに惹かれ、ヒューの見る夢に興味を持ち、同時に畏れを抱く周囲の人々についてだ。ロシア革命時に故郷を捨てた貴族を祖父に持ち、「あらかじめ失われた故郷」に憧憬を抱き、常に旅暮らしで孤独を友とするウラジーミルがもう一人の主人公だし、日本人女性・葉月やヒューを密かに慕うデザイナーのヴィーなど、登場人物は結構多い(なんと、ロアルド・ダールという名の助手までいる!)。
この中で、ヒューの心理描写は一切ない。彼は異様な体験をし続けているのに、誰よりも「正気」であり、情緒も安定していてセンスのある、バランスの取れた美しい若者である。そんな彼を、周囲は「まれびと」や、「進化した人類」とみなし、「彼は私たちとは違う人間よ」と繰り返し呟き続けるのだ。
自然界にないものを次々作り出し、文明と呼ばれる、明らかにこれまでの生物が持ち得なかったベクトルの知性を獲得した人類、元々生物としては決して強くもなく、とっくに淘汰されていてもおかしくなかった人類が地表を覆い数十億という数に膨れ上がった時、人々の無意識や精神は次にどこに向かうのか。これがこの漫画のもうひとつの軸であり、登場人物はしばしばそのことについて語り合うのだが、「その次」の象徴的なものがヒューの見ている夢であり、夢の中に登場する少女「リドル(謎)」なのだ。
登場人物たちの発するキーワードはいくつかある。
「かなしみ」と「予感」。特に「かなしみ」については、「悲しみ」「哀しみ」「悲哀」「美しさ」「真実」「現実」などあらゆる当て字まで使って何度も登場する。
つまり、この漫画の本当のテーマは、ヒューという「新人類」を目の当たりにした時に、我々「旧人類」が感じる違和感や「取り残される人類の悲しみ」であるとも読める。
物語は、一応の結末を見る。
ある日、ヒューは古道具屋で古い写真を見つける。その写真の少女は、夢の中で見た少女であり、写真には「Liddell 1879」と書かれていた。家の実在を確信したヒューは、ウラジーミルと共に、北米じゅうを回る、家探しの旅に出るのである。
ついにその家を発見した二人は家を買い取り、つかのまそこで暮らす。むろん、実在した少女はとっくに亡くなっており、「現実」での邂逅は果たせない。そして、ある晩、ヒューはついに「向こう側」へと姿を消す。ついに彼自身が「幽霊」となったのだ。ベッドの上に、暖かい人間の形をした窪みだけ残して──
それを見届けたウラジーミルは、再び新たな旅に出る。
このラストを、内田善美本人に重ねて見てしまうのは私だけではあるまい。
内田善美は「消えた漫画家」だと言われている。現在、完全に音信不通なので、彼女の作品を復刊もしくは再刊しようとしてもできないのだ、と聞いた。
ぶ〜けにこの作品が掲載されたのは一九八二年から一九八三年にかけてで、加筆の上、最終巻である第三巻が出たのは一九八六年の十月。もう二十年以上経つと思うと不思議な心地になる。
陳腐な連想であるが、彼女は「向こう側」に行ってしまったのではないか。それがヒューのように実在の姿を消すことなのか、「新人類」に意識を進化させてしまったのかは分からない。しかし、霧のような雨の中、ウラジーミルがパリに発とうとする時、「雨の向こうは冬ですか」と彼が呟き、見送る管理人の老夫婦が「行ってらっしゃいまし、よい旅を」という台詞でフェイドアウトするラストシーンは、内田善美が自分自身に向けて贈った言葉のようなのだ。
あるいは、彼女もまた「卒業」したのではなかろうか。私があの時、『ひぐらしの森』を残してすべての少女漫画を処分したように、ある意味、自分がやるべきことはやり尽くしたという感触を得た彼女もまた、「もうこれでいい」と感じ、みずから漫画家を「卒業」していったように思えてならないのだ。
(2009.6.9)
