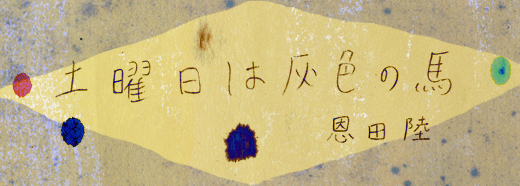
なかよし、りぼん、週刊少女フレンド、別冊マーガレット、りぼんデラックス、リリカ、花とゆめ、LaLa。いっとき定期的に買っていた少女漫画雑誌である。
なかよしはいがらしゆみこの『キャンディ・キャンディ』を読んでいる途中で対象年齢を超えたと思い、週刊少女フレンドは里中満智子『アリエスの乙女たち』が目当てだったし、別冊マーガレットはファンだった美内すずえと和田慎二が花とゆめに移行してからは脱落した。リリカはサンリオが最初から海外で売ることを目的に左開きの台詞横書き、オールカラーと美しかったがやはり当時は読みにくく、掲載作品がストーリー性に乏しかったので早々に休刊、りぼんデラックスは季刊で一条ゆかりの『デザイナー』などの総集編が目玉でやがてなくなった記憶があるので、高校を卒業して漫画雑誌を買わなくなるまでに生き残ったのはりぼん、花とゆめ、LaLaの三誌であった。
少女漫画は、私が幼年期の時には、一応学園ものもあったがそれこそ「夢」と「憧れ」を実現するためのもので、ヒロインは欧米のお譲様。コスチュームプレイ的な歴史ものも多かった。あるいはバレエ漫画やスポーツものなど求道&出生の秘密なんていう大映ドラマ的な話が定番であった。
それが、ある時から外国が舞台のものがほとんど姿を消し、身の周りの日常を描くものが主流になっていったが、それはやはり陸奥A子の登場が大きかったと思う。あのネオテニー的かつ草食的男女の登場は、それ以降の日本の少女のある層の動向すら決めたのではないかと考えてしまうほどである。それほど陸奥A子は、それまで少女漫画という舞台の、八頭身で波乱万丈のオトナの女たちを「客席から」観ていた少女たちから、熱く受け入れられた覚えがあるのだ。むろん、ストーリー至上主義の私は彼女たちが「可愛い」「可愛い」と熱く語るのに大いに戸惑いを覚え、こんな筋があるようなないような話のどこがよいのかと内心思っていたが、やがて似たような漫画が増えるにつれて馴らされていった。
しかし、ここで言っておきたいのは、確かにそれが日常を描いた学園漫画とはいえ、それはリアルな日常ではなく、ファンタジーとしての日常であったということだ。あるいは、ファンシーグッズとしての日常とでも言おうか。少女たちが少女漫画に「ほんとうの」日常のリアルを手に入れるのは更にのちの話になるし、その先駆けとなるくらもちふさこはその青春の痛さといいみっともなさといい、登場した時はごく少数派だったし、「なんでこんな嫌な話描くんだろう」と憎んでいる子も多かったと記憶している。ヒロインに親しみを覚えるのはあくまで「ときめき」や「乙女ちっくな感傷」についてのみで、おのれの醜さや痛みを共感する気はなかったのだ。
そんなわけで、私が読んでいた漫画雑誌の誌面は「どこにでもいるような普通の女の子」のヒロインに席捲され、ストーリー漫画は美内すずえと和田慎二というそれこそストーリー漫画の代表みたいな二人が移行した花とゆめに舞台を移したような気がするし、自然とそうならざるを得なかったのだろう(ここでは私が購読していた漫画雑誌に限っての印象だ。他誌では、もう少し大人っぽい漫画もあった。特に、リアルタイムで読んでいなかったプチフラワーなど小学館系の少女漫画のことは、実感としてよく分からない)
ところが、そんなりぼん本誌で一見日常的「キャンパス漫画」の顔をして登場したのが清原なつのという人であった。
『花岡ちゃんの夏休み』で登場した時、これを「私の漫画だ」と思った人は多かろう。それは、ある意味画期的な漫画だった。いつも煙草を吸っていて読書が大好きでお洒落や色恋沙汰に興味なし、という地方の国立大学の文科系学生であろう花岡ちゃんに共感した男女はとても多かった。というか、それまで「ガリ勉優等生タイプ」という一言で片付けられていた女子インテリ層を主人公にした漫画がついに登場したのである。ハゲで悪魔的に頭のいい先輩、美女で才女で男好き、という周囲のキャラクターもそれまでにない「リアル」なキャラクターだった。
この人は、その後、性をテーマにした青春ものやSFを描いてゆき(そういえば、いっとき、りぼんオリジナルという雑誌もあったなあ。ここに彼女が描いたSF『真珠とり』シリーズ、好きだった)、近年は千利休まで描いているが、そのタッチやスタンスは見事なまでに一定で、そのすべてが彼女にとっての「日常」であり、たぶん花岡ちゃんを描いている時も「キャンパス漫画」を描いているつもりはなかったのだろうなあ、と今になって思う。逆にそういう異ジャンルを「日常」に落としこめたという点でも画期的だったのではなかろうか。
もう一人、高校時代で別れを告げたりぼんで最後まで愛読していたのは高橋由佳利で、彼女の作品もまた一見普通の「キャンパス漫画」でありながら、不思議に乾いた、クールで自己客観性を備えたヒロインたちに、他の日常的少女漫画とは異なる「リアル」さを感じていた。『勝手にセレモニー』もよかったが、私が好きだったのは「倫敦階段をおりて」という短編で、その醒めた静謐さが印象に残っている。
さて、ストーリー漫画の牙城となった花とゆめ、そしてその進化形として登場したLaLaであるが、たぶん私が中学・高校時代に読んでいた頃のその二誌が最も先鋭的な少女漫画を載せていたのではあるまいか。特にLaLaは凄かった。載せている連載、短編、皆オリジナリティが濃くて面白かった。
花とゆめは創刊当時月刊で、雑誌名からいっても「上品な」少女漫画を目指していたようだ。目玉は山岸凉子の名作バレエ漫画『アラベスク』第二部や美内すずえのジャンヌ・ダルクをモデルにした歴史ものだったことからもその傾向が窺える。
しかし、ここで『アラベスク』の第二部を載せたという時から既に花とゆめの運命はきまっていたような気がするのだ。
当時の私は、人も羨むプリマとなったノンナが追われる立場となり、メソメソしてばかりいて第一部のような「のし上がっていく」カタルシスのなさに不満を持っていたが、今読み返すと断然第二部のほうが素晴らしいのである。ノンナばかりか彼女の指導者であるユーリ・ミロノフについても芸術家としての「霊感」とは何かというテーマを描いていたというのが凄いことである。
月刊時代の花とゆめはそんな感じで、かつての古きよき少女漫画も視野に入れた「上品さ」を模索していたが、その方向をはっきり決めたのは月二回刊となった時だろう。新連載二本立てとして表紙を飾ったのは、美内すずえの『ガラスの仮面』と和田慎二『スケバン刑事』だった。
以降、登場する新人もそれまで紙面を飾っていた路線とはかけ離れた、個性的でアヴァンギャルドなものになっていく。のちに『パタリロ!』で人気を博す魔夜峰央、『はみだしっ子』シリーズの三原順、『エスの解放』などシュールで前衛的な倉多江美、それこそウッドハウスばりの洒脱な英国短編を描く坂田靖子、KISS命のみかみなち、ブラックなギャグ『黒のもんもん組』とメルヘン『小さなお茶会』という正反対のジャンルを描き分けた猫十字社、などなど。どれも、編集部の寛容さと先見の明を感じさせるメンバーばかりだ。
山岸凉子は東大合格を目指すエリート高校版『風の又三郎』ならぬ『メタモルフォシス伝』や、本格ファンタジー『妖精王』を連載する。どちらも異色のテーマだが、私は時折発表された中短編に強烈な印象を持った。男女の双子の不思議な運命を描いた『パニュキス』、こんにちのサイコスリラーの奔りともいえる『スピンクス』。これらの作品の蓄積を経て結実したのが、のちにLaLaで連載された『日出処の天子』だと思う。
花とゆめでの「少女漫画のオリジナリティ」の追求は、更に広い場所である月刊誌LaLaへと持ちこされた。
LaLaがゆるぎない地位を確立するようになって、自前の新人を載せるようになると、面白いことに、花とゆめの先鋭的な部分からの揺り戻しというか、正統派の少女漫画が現れた。
『みき&ユーティ』シリーズや『あいつ』『エイリアン通り』の成田美名子や、正統学園恋愛もので人気があったひかわきょうこである。当初花とゆめが目指した少女漫画の「上品さ」が、一段階経てLaLaで達成されたような気がしてならない。特に、樹なつみが登場し、『マルチェロ物語』の豊かなストーリー性と少女漫画の華やかさの融合には子供心にも充実感を覚えたことを記憶している。高口里純とか佐々木倫子とか、独特のギャグセンスを持った人たちも出てきた。
さて、個人的にいえば、もちろん成田美名子もひかわきょうこも樹なつみも大好きだったが(特に成田美名子は、デビュー作からあっというまにファンがついて人気作家になった。絵が綺麗で、中学の漫画サークルではさんざん模写したものである)、一人私にとって大事な漫画家がデビューしている。
LaLaの新人賞「アテナ賞」は賞金も高く、レベルも高かった。そこで、佳作などではなく、堂々と本賞を獲ってデビューしてきたのが篠有紀子である。
とにかく、素人から見ても、圧倒的な画力があった。今でも覚えているのは、誰が選評していたのか覚えていないが、「絵のうまさで得をしているようなところがあります」と書かれていたことである。それほど、テクニックは完成されていた。
代表作は『アルトの声の少女』ということになろうが、私はその前段階の連載作品『フレッシュ・グリーンの季節』が好きだった。これこそ本当にホンモノの「等身大」の少女たちの物語だと思ったし、主人公の心情にこれまでにないほど共感した。
実は、私の書いた『夜のピクニック』を漫画化するとすれば、当時の篠有紀子の絵しかないなあと思っていた。もはや不可能な話ではあるが。
ここまでが、私の「少女漫画時代」を巡るおおまかな話である。大学生以降、漫画は単行本でしか買わなくなり、少女漫画は「点」でしか読まなくなってしまったけれど、小学生から高校生まで、文字通り少女漫画と暮らしていたといっていい。
こうして振り返ると、リアルタイムで雑誌で漫画を読むというのはとても面白い体験だった。もはやこんなふうに全身全霊を込めて漫画を連載で読む経験はできまい。なにより、正真正銘の「少女」だった時代に、最も進化を遂げた時期の少女漫画と共に成長できたのは時代のめぐりあわせというか、ラッキーだったとしかいいようがない。
もっとも、私の場合、週刊マーガレット系や小学館系、秋田書店系がすっぽり抜けている。それというのも、当時の私は漫画を「借りる」ということができず、買ったものしか読めなかったからだ。さすがに高校生の頃には少しずつ平気になったが、とにかく「返す」のがつらくてたまらなかったのである。今にして思えば誰かと協力してそちらの系統を借りればよかったとつくづく残念に思う。だから、ここで告白するが、私は『ベルサイユのばら』も『SWAN』も紡木たくも読んでいないのだ。萩尾望都、槇村さとる、『エースをねらえ!』、くらもちふさこ、青池保子、『悪魔(デイモス)の花嫁』、吉田秋生はどれもコミックスで読んでいる。今となれば「オトナ買い」できるのだが、未だに「私のカバー範囲ではなかった」というコンプレックスがあるせいか、書店で文庫の背表紙を眺めながらも買うことができないのだ。
更に、高野文子、岡崎京子、魚喃キリコ、安野モヨコ、よしながふみあたりになるともはや私の中では「少女漫画家」ではないので、私の少女漫画時代はそこまでということになる。
いやはや、長々と個人的な回想におつきあいいただき、たいへん恐縮である。
ところで、購読してはいなかったが、ずーっと気になっていた少女漫画雑誌がひとつあった。
ぶ〜けである。LaLaとはまた少し異なるカラーのオリジナリティと少女漫画らしさに興味を持っていたし、松苗あけみや水樹和佳(水樹和佳子)が描いているのをちらちらと横目で見ていた。
そして、何より、内田善美が代表作のほとんどを描いていた雑誌であった。
いよいよ次回は内田善美について語らなければなるまい。
内田善美こそは、私にとって「最後の少女漫画家」だからである。この言葉の意味も含め、この項目、もう一回続きます。
(2009.2.6)
