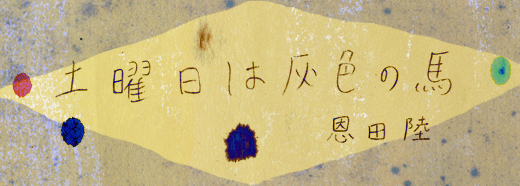
(1)
子供の本には挿絵が欠かせない。
かつて本というものに触れ始めた時は、本というのは「絵があるもの」で、絵を見るために本を開いていた。絵のない本など、その存在が理解できなかったものだ。
小学校に上がるまでは、絵本の中の世界がそのまま脳内イメージになっていて、つぎはぎになった絵本の絵の世界に生きていたような気がする。
「ちいさいおうち」に流れる、何世代もの長い長い時間。
「せいめいのれきし」の光と影に満ちた荘厳な時間。
「てぶくろ」の、ミクロでいてマクロな生き物の世界。
「ぐりとぐら」の、巨大な卵からできたホカホカのかすてら。
「ももいろのきりん」の、色とりどりのクレヨンがなる木。
毎日毎日繰り返し飽きもせずにページを開き、あげくの果てにはページの外の話の続きを自分でこしらえたり、薄い絵本に不満を抱いて、いつまでも終わらない絵本があればいいのにと夢想していた。
絵本はもちろん、挿絵とセットになって記憶されている名作児童文学は多い。『不思議の国のアリス』『クマのプーさん』『ナルニア国ものがたり』『星の王子さま』『ドリトル先生シリーズ』『エルマーのぼうけん』、などなど。もはやこのレベルになると本文と分かちがたく、まさに話と一体化して読者のイメージを確固たるものに築き上げてきた。
今でも細部まで覚えている本に、牧村慶子が絵を描いた『石の花』がある。大判のフルカラーの絵本で、職人である主人公が「細工をするための素晴らしい石がある場所」に行き、石を掘る場面で、その石のかけらの美しい色とすべすべした触感までが伝わってきて、今でも、当時想像したひんやりした石の触感が思い浮かぶほどなのだ。
本に親しむにつけ、だんだん長いものが読めるようになると、少しずつ挿絵が減ってゆき、ついに全く絵のない本を読んだ時にはずいぶん大人になったような気がしたものだった。今では、小説に絵が付いているほうが「イメージを限定してしまうのになあ」と思う。
(2)
私の絵の趣味は、どうも昔からダークだったらしい。とにかく、毒のある絵が好きだった。子供の頃に強烈に印象に残っているのは、宇野亜喜良、井上洋介、片山健、小林泰彦、堀内誠一、味戸ケイコらである。
宇野亜喜良は子供の頃から私のアイドルである。コケティッシュで大人っぽく、官能的なのに寓話的で。今江祥智『さよなら子どもの時間』、フォア・レディースという変形版シリーズで出ていた立原えりかの『恋する魔女』、ジェームズ・サーバー『たくさんのお月さま』。シンプルな、時間と空間が地続きになったようなタッチにとても憧れた。お絵かきの好きだった私はよく真似したけれど、あんな線はとても引けなかった。小説家になって、『ネバーランド』を連載する時、「誰か希望する絵描きさんはいますか」と聞かれ、真っ先にその名を挙げてイラストをお願いできた時は、子供の頃からこの日までが繋がっていたように思えて、感無量だった。
小林泰彦は、もちろん小林信彦の『オヨヨ大統領シリーズ』の挿絵。今にしてみれば、イラスト・ルポのはしりみたいな、サブカル系の方だったのですね。漫画のコマのように手書きの枠があって、隅っこに落款のように「ヤスヒコ」と描いてあるところがカッコよったのだ。
堀内誠一はずば抜けたデッサン力で谷川俊太郎訳の『マザー・グースのうた』など、ヨーロッパを題材にしたイラストが抜群にうまかった。子供向けの絵本もいっぱいあったけど、『グリム童話』で呪文を唱えるとどんどんおかゆが溢れてくる鍋の話があって、それを止める呪文を忘れて町中がおかゆだらけになるという、ブリューゲルみたいな絵が私の印象に残っている。もちろん当時は、有名なアートディレクターだったなんてことは全く知らなかった。
ええ、どれも真似しましたとも。描けなかったけど。
井上洋介、片山健は福音館書店の出していた「こどものとも」シリーズの『だれかがぱいをたべにきた』、『もりのおばけ』などどれもダークな話が好きだった。だいたい、私は先に挙げた世界名作児童文学でも『エルマーのぼうけん』の絵が好きなのだが、宇野・小林・井上などのシンプルな線を主体にしたイラストの路線と、輪郭を描かず影で表現するタイプの路線とが好きらしい。『エルマーのぼうけん』や片山健、味戸ケイコなんかはこの路線だ。今は別の画家のものに替わってしまったが、私が持っている版の『チョコレート工場の秘密』もこの路線で、床に工場のホースがいっぱい並んでいる場面なんか異様に偏愛していたなあ。
最近、福音館書店から出た月刊絵本「こどものとも」の創立五十年記念号『おじいさんがかぶをうえました』で歴代の「こどものとも」を眺めていたが、私の記憶に残っている絵本というのはどれもこれも狙ったようにアクの強いマイナー感漂う不気味系ばかりで、メインストリームの爽やかなもの、可愛いもの、感動的なものは全く覚えていないところがやはり三つ子の魂百まで、という感じである。
(3)
更に、私のイラストの趣味に決定的な影響を与えたのは、今はもう休刊してしまったが、やなせたかしの責任編集でサンリオから出ていた「詩とメルヘン」だった。「アンパンマン」の初出はこの雑誌である。やなせたかしの表紙がいつも鮮やかで、色が本当に素晴らしかった。小学校二年生くらいから高校生まで購読していたし、当時のバックナンバーは今も全部とってある。
全く広告を載せず、投稿された詩で構成するという今では珍しくないタイプの雑誌だが、大判で、いい紙を使って、カラー印刷、見開きにひとつの詩でそれにイラストを付ける、という贅沢な造りだった。童話は原則としてプロが書いていたが、私は別役実をこの雑誌で知ったので、最初別役実は童話作家だと思っていたのである。「流れる町」や「愛のサーカス」など、今読んでも凄味のある美しくも恐ろしい傑作が素晴らしい挿絵付きで掲載され、強い影響を受けた。
ここにはもちろん宇野亜喜良も描いていたし、林静一、飯野和好、スズキコージ、滝野晴夫、北見隆、牧村慶子、東君平、黒井健らそうそうたるメンバーで、毎月舐めるように絵を眺めていた。葉祥明や東逸子もここに登場してからブレイクした気がする。
ジャック・プレヴェールの詩や中原中也の詩を特集したり、アンドレ・モーロワやジュール・シュペルヴィエルの短編を絵本ふうにイラストをつけたり、井上陽水らフォーク歌手の歌詞をシリーズで載せるなど、なかなか渋い企画もあった。グランマ・モーゼスの絵を日本で最初に紹介したのもこの雑誌だったと思う。
のちにプロのためのイラストコンクールができて(毎月開催していて、実際に掲載された詩の中から自分で一枚選んで絵を付けるという審査方法。読者投票なども考慮して、通年で年間のグランプリを決める、という面白い形式だった)、おおた慶文、早川司寿乃、きたのじゅんこ、小谷智子らもここから出てきた記憶がある。特に、私は登場してきた時から早川司寿乃が好きで、彼女の応募作である、「ゆびめがね」という詩につけた、セピア色の画面の中央の丸い窓の向こうに波打つ海が見えるという絵を今でもよく覚えている。
(4)
既に絵本作家として認められた人も、どちらかといえば「詩とメルヘン」では、ダークで実験的なものを描いていたような気がする。「詩とメルヘン」は投稿者が大人中心だったこともあり、かなり大人っぽかったからだ。
中でも特に強い印象を受けたのが、上野紀子と味戸ケイコだった。
上野紀子は『ねずみくんのチョッキ』など、「ねずみくんシリーズ」で既に地位を確立していたけれど、私は断然もう一人のメインキャラクターである「黒ぼうしちゃん」のファンだ。この子はいつも黒づくめの格好をしていて、文字どおり黒い幅広の帽子をかぶっているため顔に影が落ちていて表情が見えないという、幼少の少女ではあるがかなりゴスロリが入っている、上野紀子の作品ではお馴染みのキャラクターだ。ただでさえ絵本業界では異色のキャラクターであるが、中でも「詩とメルヘン」で最初に見た「室内旅行」という八ページの特集の、ルソーばりの濃くて妖しい絵の印象が強い。やはり、生まれ持った性分か、二面性のあるアーティストの作品を見た場合、専らダークサイドに反応してしまうようなのである。
そして、「詩とメルヘン」といえば、私にとっては味戸ケイコである。「光と影を描く画家」という言葉がこれほどぴったりする人はいないだろうと思われるほど、味戸ケイコの描く夕暮れやカーテン越しの光の鉛筆画は私を魅了した。
残念なことに、もう亡くなられてしまったが、いつも安房直子の童話(最近全集が出た)とのセットで記憶している。彼女の童話がまた不穏で美しく恐ろしく、味戸ケイコの絵とぴったりマッチしていた。このコンビは最強だったといえよう。
このゴールデンコンビは「詩とメルヘン」でたくさんの作品を残したが(最近、瑞雲社から『夢の果て』という本にまとめられた。当時の担当編集者の熱意によるもので、ベストな形だと思う。が、絵のサイズが小さくてさみしいのと、味戸さんが結構新たに絵を描き直しておられるのが個人的には残念。私としては、「詩とメルヘン」のサイズで、当時の掲載のままの組みとイラストでムック版としてまとめられたものが欲しい!)、私のお気に入りは「夢の果て」「声の森」「小鳥とばら」だ。
「夢の果て」は不思議なアイシャドウをまぶたに塗って眠るといつも同じ夢を見るという話で、少女は夢の続きを見るために毎晩アイシャドウを塗って眠る(肌によくないと思うけどね)。やがて夢の中でついに「探していた」と思える男性に出会うが、アイシャドウをもう使い切ってしまい、あきらめきれずもう一本手に入れようとアイシャドウの製造元に出かけていくと──という話。
「声の森」は、中に入り込んだ者の出すあらゆる音を真似する魔の森に入り込んだ少女がどうやって森から脱出するかという話。
そして、「小鳥とばら」は、バドミントンの羽根を追って町外れの謎のお屋敷に迷いこんだ女の子が不思議な母と息子に小鳥とばらのパイを食べさせられて──という話である。
安房直子の話は、異界との接点をテーマにしたものが多く、どれも夕暮れどきに終わりを迎える。その「あわい」と味戸ケイコの描く黄昏のイメージが渾然一体となって、私が世界に感じている違和感と畏れを目の前に見せてくれていたように思えるのだ。
子供の頃に見ていた絵本の中の世界は、今もなお巨大な背景となって私の頭の中と繋がっているし、その世界をもっと理解したい、味わいたいという願望を満たすために、私は小説を書き続けているのかもしれない。
(2007.1.26)
