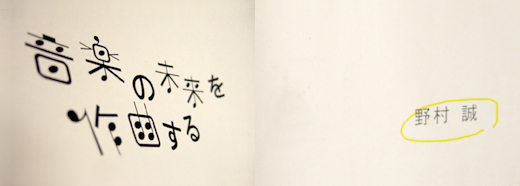
1 楽器の個性、人の個性
大阪のガムラン・グループ「ダルマ・ブダヤ」から、ガムランのための作曲の委嘱を受けたのは、1995年の終わりだった。ガムランのために新曲を作曲して欲しい、その作品は、京都、大阪、神戸で演奏した後、インドネシアの4都市(ジャカルタ、バンドン、ジョグジャカルタ、スラカルタ)でも演奏するという。インドネシアの伝統音楽であるガムラン音楽について、ぼくは専門的な知識は皆無に近かった。しかし、ガムランについて知らないからこそ作曲できる音楽もあるはずだと考え、思い切って引き受けることにした。
当時のぼくは、本当にガムランについて無知だった。知っていたことと言えば、ペロッグ、スレンドロという二つの主要な音階があり、西洋音階とは全く違ったチューニングシステムを持つこと。バリ、ジャワ、スンダなど、いくつかの異なった様式があること。ほとんどの楽器が金属製の打楽器であること。せいぜいそれくらいだった。楽器の名称すら知らなかったし、どの楽器からどんな音が出るか、どの楽器がどういう役割を果たしているかも、全く知らなかった。だから、知らない利点を生かすために、ぼくは敢えて勉強せずに、いきなりダルマブダヤのリハーサルを見に行くことにした。
ダルマブダヤは、インドネシアツアーのためのリハーサルをしていた。マイケル・ナイマン(イギリス)、ヴィル・エイスマ(オランダ)、ポーリン・オリヴェロス(アメリカ)、松永通温(日本)など、ジャワ伝統音楽とは無縁の西洋音楽の作曲家のガムラン作品が演奏されていた。これらの音楽は、五線で作曲され、西洋音楽的なスコアで書かれた音楽だったが、せっかく5線譜とは無縁のインドネシアの楽器のために作曲するのに、五線で作曲するのは、なんだかもったいないし、成功していないように感じた。とにかく、ぼくは五線は使わずに作曲しようと考えた。では、どうするか。
まずは、ガムランの数字譜の書き方を覚えた。ペロッグ音階は、「1234567」、スレンドロ音階は「12356」の数字で表される。もちろん、ペロッグの1と、スレンドロの1は、全く違った音で、単に1番目の鍵盤という意味以上のものではない。ぼくは、ガムランでやってみたいアイディアを、とにかく数字を使って書いてみた。五線紙ではなく、無地のスケッチブックに書いた。それは、数字と文字が混在したお手紙のようなアイディアノートになった。
こうしたアイディアを持って、月1回、通称「野村デー」と呼ばれるセッションを、ダルマブダヤのメンバーと行った。実際に音に出してみることで、いろいろな発見がある。
「この楽器とあの楽器は、思ったより音が混ざらないんだ。」
「この楽器は速いパッセージは演奏しにくいんだ」
など、楽器について色んなことが分かってくる。と同時に、
「この人はコミカルな人だなぁ」
「この人は、リズムのキープが得意だな」
「この人はアドリブが得意だなぁ」
など、演奏者一人ひとりの個性が見えてきた。楽器の特性を探る作業をしていたつもりだったのに、気がついたら演奏者の個性を探る作業になっていた。例えば、クンダンという太鼓を山崎さんという奏者が演奏する。クンダンをジャワ人が演奏したら、きっと全然違ったノリだろうし、イギリス人が演奏しても全然違ったノリだろう。でも、ぼくは、山崎さん以外の人がクンダンを演奏したのを聴いたことがない状態で作曲していた。つまり、当時のぼくにとって、クンダン=山崎さんだったのだ。山崎さんの魅力とクンダンの魅力が最大限に生かされるにはどうしたらいいか。結局、作曲する時には、ずっと演奏者の顔を思い浮かべながら作曲することになる。作曲するとは、楽器の魅力と同時に、演奏者の魅力をどうやって演出するか、ということのはずだ。これは、pou-fouをやっていた時から感じていたことなのだが、ぼくは、人の個性にもっと特化して作曲していきたいと、考えるようになっていった。
2 不完全な開かれた作品、「踊れ!ベートーヴェン」の発見
こうして、人と関わりながら作曲しているうちに、せっかくインドネシアで公演するのに、インドネシアの人と関わらないのは残念な気がしてきた。ぼくの曲には、インドネシア人が参加する場面を作り、ぼくの曲の中で日本人とインドネシア人が交流できるようにしよう。当時、イギリスで子どもたちと共同作曲を実践して帰国したばかりだったので、インドネシアの子どもたちが参加できる場面を作ることにした。では、どうやって?
インドネシアの子どもたちのパートを全部作曲してからインドネシアツアーに行くのが、一番効率がいい。でも、人の個性に特化して作曲しようと考え始めていたぼくは、インドネシアの子どもたちとも「野村デー」をやってみたいと考えた。そこで、曲の中間部分は自由度を大きくして、現地の子どもたちと作曲した場面が後からはめ込めるようにしよう。方針が全部決まったところで、ぼくは20分強の大作ジャワ・ガムランと児童合唱のための「踊れ!ベートーヴェン」(1996)のスコアを、一気に書き上げた。
スコアを書き上げたら、普通、作品は完成するはずだが、この作品は未完成な作品だ。なぜなら、中間部分は、演奏する地元の人と新たに作曲して、交流するように楽譜に書いてあるからだ。だから、この曲には、演奏する度に違った人が参加する。丹後と京都では、シンガー・ソングライターのTASKEが共演、大阪と神戸では、貝塚少年少女合唱団が共演、ジャカルタでは、小学生アンクルン楽団、ジョグジャカルタ、スラカルタでは、プランバナン中学の子どもたちが参加した(その後、京都では、子どもたちの大正琴、水口では、ワークショップ参加者のだるまさんが演劇ゲーム、大垣では、作曲家の三輪眞弘のコンピュータ・アルゴリズムが共演)。だから、中間部分は毎回違ったパートとして、その都度、作曲されることになる。作曲作品の楽譜に、「この場面は新たに作曲してください」と書き込んだことで、作品が創作の場、交流の場としても機能し始めたのだ。
こうして上演する度に演奏が変わっていく過程を、ダルマブダヤのメンバーも楽しんでくれたようだ。京都公演の前に、松永作品に木琴奏者として客演していた野口さんが、「野村さんの曲にも、どこかで参加したいので、パートを一つ増やして欲しい」と願い出てくれた。そこでぼくは、新たにデムンという鉄琴のパートを一つ増設した。また、ジャカルタ公演の本番直前に、「野村さん、この太鼓買ったんですけど、曲のどこかで使えませんか?」とメンバーが言う。お土産として買った太鼓だけど、せっかくだから、どこかで使おう。新たに場面を増設する。さらには、バンドン公演、ジョグジャカルタ公演、スラカルタ公演では、せっかくだから現地の超一流の太鼓奏者とセッションしたいのだけど、どこか曲に増設できないか、ということになる。現地の太鼓奏者が、即興的に参加できる場面を設けることになった。
こうしたことに気をよくしたぼくは、ジョグジャカルタ公演では、観客が参加する場面を設け、観客にも声を出してもらった。旅をしながら作品がアップデイトされていき、その場で出会った人、関わった人の足跡が作品に残っていく。そして、インドネシア国立芸術大学ジョグジャカルタ校で行われたワークショップでは、「踊れ!ベートーヴェン」を聴いてもらった後に、芸大の伝統音楽科の講師陣たちに、「踊れ!ベートーヴェン」を真似してもらった。「踊れ!ベートーヴェン」は、日本人とインドネシア人が共に参加して創作していく場としての作品だった。
不完全な作品だからこそ、作品がアップデイトされていく。作曲家は作品を構成しつつ、しかも未完成のまま可能性を開いていくことが必要なのではないか。また、未完成でありつつも、多くの人々の創造性を刺激するだけの魅力を持ち合わせた作品を作ることこそが、作曲家の仕事なのではないか。
3 私の作品か? 私たちの作品か?
イギリスの作曲家Peter Wiegoldは、スラカルタに滞在してガムランを学んだ時、ジャワの演奏家からガムランの作品を作曲して欲しいと頼まれた。そこで、作曲したところ、演奏家はさっそく音に出してみた。そして口々に、
「この場面をもう少し長くしてみよう」
とか、
「こういうイントロを付け加えよう」
とか、
「ここは省こう」
などと、作曲者に断りもなく曲に手を加え始めた。そして、Wiegoldは、この曲は「私の作品」だと思っていたのに、そうではなく「私たちの作品」だったのだ、と気づいたと言う。ジャワの音楽家は、個人の作品という感覚で音楽をしているわけではなく、複数の個人の感覚の融合としての音楽をしているのだ。西洋音楽は、一人の作曲家が作曲した個人の音楽を、一人の指揮者が統率して、一つのイメージを形成していく。しかし、ガムランは、時に20人以上で演奏されても、指揮者はいない。あくまで、複数の演奏家たちの「あいだ」に音楽が生成する。
こうしたジャワでの経験に着想を得たWiegoldは、作曲家に交響曲の1ページ目だけの作曲を委嘱し、その続きはオーケストラのメンバーと即興的に組み上げていく試みをしている。ここで作曲家の役割は、叩き台を作ることで、演奏者全員が創作に加わっている。
「ダルマブダヤ」の代表で民族音楽学者の中川真さんは、「踊れ!ベートーヴェン」初演の翌年(1997年)に、インドネシア芸術大学ジョグジャカルタ校に、客員教授として半年間滞在する。ジャワ滞在中、中川さんはガムラン現代音楽を、現地の音楽家と演奏しようと試みる。演奏に加わったのは、ジャワ・ガムランの超一流の演奏家ばかりだったそうだが、西洋音楽の発想で書かれた楽譜の音楽を、何度やっても彼らは演奏できるようにならなかったと言う。中川さんは愕然としたと言う。
やはり、ジャワ・ガムランというのは、個人の音楽を演奏するのではなく、その場にいる複数の個人の音楽性を融合して作る音楽なのだと思う。そのことを再確認するために、中川さんは、もう一度、ジャワ・ガムランの伝統を踏まえてみようと考えた。それは古典に回帰するという意味ではない。ガムランという音楽をしている本質とは何か? エッセンスとは何か? それを体感した上で、インドネシア人と共有できるガムラン現代音楽を作りたいということだ。楽譜や指揮者という西洋の発想では、「私の作品」としてのガムランしか生まれない。では、ガムラン的な「私たちの作品」を生み出すにはどうしたらいいか?
中川さんは帰国すると、自らダルマブダヤを退団し、新しいガムラングループ「マルガサリ」を立ち上げた。そして、2年間現代音楽を封印し、ジャワの伝統音楽を演奏し続けた。そして、2000年、一切楽譜を書かず、伝統音楽のように、全てを口伝えで新曲を作れないか、とマルガサリから委嘱があった。
「私の作品」が「私たちの作品」になるための鍵として、中川さんは、楽譜を排除することを考えた。楽譜というものがあると、作品は固定化されて定着する。では、楽譜をなくすとどうなるか? そうした実験として作曲したのが、「せみ」だった。「せみ」の全てのパートは、口頭で伝えられることを前提に作曲された。例えば、曲の終わりでは、各自がそれぞれ楽器を鳴らす。そして、自分の鳴らした楽器の音を聴き、そのピッチで「みーん」と一息で歌う。歌い終わったら、また、別の楽器を鳴らし、同様に続ける。すると、全体としては、複雑なハーモニーの「みーん」が時々刻々と響きを変化させていき、その間に楽器の音が、ランダムにカンとかコンとかゴーンと鳴り響く。また、曲は、スコアのように小節でくぎられるのではなく、誰かが合図を出すと、それに呼応するように誰かが別のフレーズを演奏するなど、関係性で成り立つようにできている。
しかし、譜面のない作品「せみ」は、野村誠作曲作品(「私の作品」)であり、「私たちの作品」にはならなかった。曲の仕組みは全て野村誠が考えたもので、演奏者はそれを教わって演奏していた。
「野村さん、ここはもっと変えましょう。」
なんて提案してくる人もいなかった。楽譜があった「踊れ!ベートーヴェン」の方が、演奏者から提案がどんどんあって、加筆・変更し、よっぽど「私たちの作品」になっていたと思う。
当時の「マルガサリ」は2年間ジャワの伝統音楽を学び続けていたが、ジャワの音楽は「私たちの音楽」として消化できていなかったと思う。あくまで、インドネシアの人たちの音楽で、それをインドネシアから教わっている感覚が強かった。同様に、野村誠の音楽も、野村誠から教わっている感覚が強かったと思う。演奏者は、何を演奏していても、自分自身の音楽として消化する上で演奏しなければ、それは「私たちの音楽」にはなれないはずだ。そこで、「私たちの作品」として、野村誠とマルガサリは、ガムランシアター「桃太郎」の創作に取り組むことになる。
4 「ペペロペロ」〜私たちの作品へ
「せみ」を完成させた翌年、マルガサリと5年計画で始めたプロジェクトが、ガムランシアター「桃太郎」の共同創作だった。ここでは、個人の作曲家の作品としてではなく、「私たちの作品」と各自が認識できる作品を徹底して目指している。ぼくたちは何をするべきか?
「踊れ!ベートーヴェン」もWiegoldの場合も、叩き台になる楽曲は、作曲者が提示している。作曲家が叩き台を作り、それをアレンジしていく作業は比較的簡単にできる。しかし、個人が叩き台を作るのではなく、最初のアイディアを作るところから全てを共同作業で作ってみることはできないか? と考えた。そこで、ぼくは敢えて叩き台を一切用意せず、アイディアを練るところから、マルガサリのメンバーと共同で作曲していくことを決意した。その結果、「桃太郎」は、戯曲なし、楽譜なし、音楽も台詞もダンスも、全てはワークショップのようなリハーサルから誕生するという形式を取ることにした。
これは、20〜30人の大所帯のマルガサリとの共同作曲は、4、5人での共同作曲とは全く違う体験だった。4、5人ならば、比較的簡単に話し合いもできる。しかし、20人ともなると、話し合いも容易ではない。非効率極まりない。叩き台がない。演出家も指揮者もいない。全てを話し合いながら、実演しながら試行錯誤で決めていく。当然、意見はまとならない。
「私の作品」を「私たちの作品」にしようと始めた試みだが、メンバー間の人間関係に少しでもヒエラルキーができると、発言力の大きい人の意見が通ってしまう。これでは、結局のところ「私の作品」に回帰していくではないか。創作作業は、人間関係のあり方と大きく関係してくる。
2001年に創作の「桃太郎第1場」では、20人全員で創作するのではなく、5〜10人程度のグループに分かれて「しょうぎ作曲」を行い、そこでできた音楽をベースに再構成した。しかし、作品を構成していくアレンジは、野村誠が主導で進められたし、メンバーは受け身な姿勢も大きく、「私たちの作品」と言えるかというと疑問だ。
2002年に作曲の「桃太郎第2場」では、ガムランの楽器を離れて、声や身体の動きから創作作業を始めた。また、代表の中川真さんの研究フィールドである「サウンドスケープ」や、「お田植え神事」なども作品に盛り込みたいとの要望もあったので、取り入れた。こうして積極的にアイディアを提案してくるのは、中川さんなど一部で、創作プロセスとしては、野村誠、中川真など、ごく一部の人が主導で進んでいった感は否めなかった。
2003年、「桃太郎第3場」に取り組む前に、ぼくは、いずみホールでのガムランコンサートのために、新作の委嘱を受けた。この作品もマルガサリが演奏することになっていた。この新作で、譜面を書いたり、たとえ譜面を使わなくても野村が叩き台を作った音楽を作ったりはしたくなかった。それは、「桃太郎」が「私たちの作品」として成立することを否定してしまいそうだったからだ。そこで、ぼくは、決意した。マルガサリとの最初のリハーサルで、こう言ったのだ。
「これから来るリハーサルでは、毎回、皆さんとガムランで遊びます。どんなアイディアでも、ぼくが曲にしてみせますから、しょうもないアイディアでも、提案してください。完成像のことを全く気にせずに、好きにガムランで遊んだり、好き勝手な提案、要望をして野村を困らせてください。それでも、作曲家として、ぼくは作品を構成してみせます。」
この発言がメンバーに安心感を与えたのか、リハーサルでは、次々にナンセンスなアイディアが出てくる。そして、それを大まじめにやってみる。ガムランの楽器を桶に見立てて、そこに向けて「おえ」と嘔吐する。「蚊取り線香」と言って、蚊の鳴き声をルバブ(弦楽器)で模倣する。「相撲取り」と言って、「のこった、のこった、勇み足」と言った後に、全員で座布団を放り投げる。創作の場では、どんどんアイディアが生まれ、それらを一切却下せずに、全てを作品として構成していく作業は、難しいし、面白いし、新鮮だった。朝日新聞には、「関西発!笑うガムラン」と評され、コンサートのアンケートでは、「最高」と「最低」に二分した。「ペペロペロ」と題されたこの曲は、一切の叩き台もないところから全て共同で作り上げた初めてガムラン作品だった。ついにぼくらは「私たちの作品」の地平に辿り着いた。
「ペペロペロ」の直後に作った「桃太郎第3場」では、ガムランでロック風、演歌風、ミュージカル風など、様々な音楽形態を模倣したりする。もはや、ガムランはインドネシア人から教わるものでもなければ、野村誠から教わるものでもなく、メンバー一人ひとりの音楽になっていた。そして、自分の身近な感覚で、各自が思ったことを提案して作っていく。マルガサリのメンバーは「桃太郎」の創作に積極性を増していく。「演奏者が役者にもなり、作曲もし、アレンジもし、美術も作り、音楽グループの枠を超えて、音楽シアターグループ化し始めた。
2005年に一応の完成に達した「桃太郎」は、その後も「私たちの作品」として上演の度に改訂され続け、2008年夏には、インドネシアの3都市(ジャカルタ、ジョグジャ、スラバヤ)で公演を成功させた。
5 再び、楽器の個性と人の個性
「私の作品」を「私たちの作品」にする時、必ず浮上してくるのが人間関係だ。メンバーの間に上下関係ができると、発言力の大きい人の意見が、自信のある人の意見が通ってしまう。議論の得意な人の意見が通ってしまう。そうなると、結局「私たちの作品」ではなく、一個人の色の強い「私の作品」に限りなく近づいていく。
では、一個人の意見を押し付けないように各自が遠慮する。却下を禁止する。すると、お互いにほめ合ったり、讃え合ったりするのだが、本当に本心からいいと思っているのだろうか? ただ、なんとなく当たり障りのないことを言って、場を繕っているのではないか?と思えてくる。刺激的な創作活動というより譲り合いの場になり、誰もが自分の意見を主張しなくなり、消極的な参加になっていく。
それでは、本当に研ぎすまされた作品は生まれない。もっと積極的に創作に関わって意見をぶつけ合おうと考える。作品の細部にまでこだわりを持って意見をぶつけ合う。当然、自分と価値観の違う人の意見を受け入れることは妥協になる。意見は食い違う。食い違い迷路に入っていく。作品の質を高めるために、グループは分裂するか、特定の個人を攻撃したり排除したりすることになる。その結果、研ぎすました作品を作るためには、価値観の似た人で集まって作品を作る、価値観の食い違った人は排除していくことになる。
こうした問題を考える時に、もう一度、最初に掲げたテーマ「楽器の個性、人の個性」について、ぼくは考えてみることにした。作曲家は、どんな音色の楽器を組み合わせるか、楽器編成の組み合わせで、独自の世界を構築したりする。敢えて同種の楽器を多様して(チェロ8重奏、鍵盤ハーモニカ8重奏)極端に一色になったサウンドを作ることもあれば、楽器の意外な組み合わせで(例えば、ホセ・マセダは、竜笛とコントラファゴットとガムランと竹と児童合唱を組み合わせた)独特なサウンドを作ることもある。楽器の編成の仕方に作曲家の個性が出てくる。
しかし、ダルマブダヤとの体験で感じた「楽器の個性」以上に「人の個性」に着目してみたら、どうなるだろう?「私たちの作品」づくりの場には、どういう個性がいて欲しいだろう? どういう好みの違いや、どういう意見の食い違いが生まれ、相互作用が起きる場にするか?
人間関係の展開やトラブルまで想定しながら、メンバーを集め創作の場を設定する。それは楽器編成を考えるのと同じく、いやそれ以上に重要な作曲作業だと思う。
(次回へ続く)
2008.10.17 update
