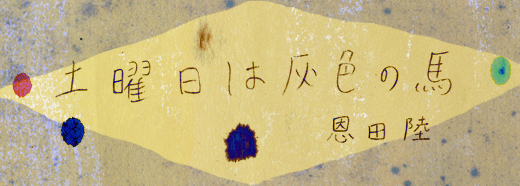
「伝奇」なる言葉を広辞苑で引くと、「?不思議なこと、珍しいことを伝え記したもの」という説明文が出てくる。そのまんまだ、と思うがそのまんまのことに今も魅了され、そのまんまのことを書いて生活しているのだから文句は言えない。
しかし、今の日本で普通に「伝奇小説」と言えば、山田風太郎とか柴田錬三郎とか、アクが強くてやや荒唐無稽な味付けをした歴史もの、というイメージではないだろうか。
ただ、私の考える「伝奇小説」は、次の条件が満たされていなければならない。
一、 歴史や考古学、民俗学などの薀蓄が満載されている。
二、 作者のオリジナリティある、歴史や事物に対する解釈や新説が披露されている。
逆にこの二つが満たされていれば、私は割に広い範囲で伝奇小説とみなしている。
たとえば、時代小説と伝奇小説は境目が曖昧だけれど、忠臣蔵を諜報戦&心理戦として描いた『四十七人の刺客』(池宮彰一郎)や、吉原を治外法権の要塞とみなした『吉原御免状』(隆慶一郎)なんかは私の中では伝奇小説に近い位置づけだ。
フィクションとノンフィクションの中間に位置すると思われる明石散人『宇宙の庭』(龍安寺石庭の暗喩を解き明かす)とか世界的ベストセラーになったグラハム・ハンコックの『神々の指紋』(地軸の移動でこれまでに何度も高度な文明が滅亡しているとする説)も伝奇小説。
もちろん、ダン・ブラウンの『ダ・ヴィンチ・コード』とか夢枕獏の『陰陽師』もバリバリ伝奇小説。
歴史ミステリはほとんどそうで、井沢元彦の『猿丸幻視行』とかウンベルト・エーコの『薔薇の名前』も堂々たる伝奇ミステリ。最近はノンフィクションでも人類学者中沢新一の『アースダイバー』とか宗教学者鎌田東二の『聖地感覚』なんかも伝奇だ。あ、梅原猛は立ってるだけで伝奇。
言葉は悪いが、妄想すれすれでも熱く筋の通った自説を展開してくれればすべて伝奇なのだ。
「伝奇」的なものになぜ人は惹かれるのか。子供の頃、「世界の七不思議」とか「謎の古代文明」にわくわくした気持ちは今も変わらない。
思えばいろいろ読んできた。
角川文庫のオレンジ色の背表紙、デニケンの『未来の記憶』、トレンチ『地球内部からの円盤』に始まり(地球空洞説って今もあるのだろうか)、手塚治虫の『ライオンブックス』(エジプト古代文明は宇宙人の遺産、という話があった)、ジュール・ヴェルヌにコナン・ドイル(この二人はSFというよりやはり伝奇)。
日本SFの半分くらいは伝奇小説だった。半村良に山田正紀、小松左京に光瀬龍。遠い過去は遠い未来と一緒。あまり過去のないアメリカ合衆国に未来を語るSFが栄えたのも当然だろう。
強烈なインパクトがあったのは、手塚治虫の『三つ目がとおる』とNHKの『未来への遺産』だ。『三つ目がとおる』は額の三つめの目にバンソウコウを貼った少年写楽保介が古代文明の謎を探る話だし、『未来への遺産』は世界中の遺跡を巡る思索紀行。特に、奈良の飛鳥とイースター島に夢中になって、亀石が回って大和一円が泥の海に沈む話とか、イースター島に伝説の鳥人が飛んでくる話とか、漫画で書いていた。それまでにも森本哲郎のイースター島やタッシリ・ナジェールの紀行文なんかも読んでいたが、ヘイエルダールの『アク・アク』を難しいと思いながらも一生懸命読んだ。
それから中学、高校生あたりになると梅原猛の『隠された十字架』にゾクゾクし、現代随一の伝奇作家、高橋克彦が登場して『竜の柩』とか『刻迷宮』を夢中になって読むという経過を辿り、現在に至るのである。
小説家として中南米を訪れ、マヤ文明やインカ文明の地を目にした時は感無量。あのUFOを操作する図として有名な壁画のあるパレンケ、春分と秋分の日にピラミッドに光の蛇が現れるチチェン・イッツァ、『スター・ウォーズ』のロケ地ティカル、謎の空中都市マチュ・ピチュを見られて伝奇ファンとしては本望。その紀行文を一冊にまとめて、雑誌「ムー」から取材申込があった時は「私も偉くなったものだ」としみじみ思ったのであった。
さて、ここまでは前振りである。
しばらく伝奇的なものから遠ざかっていたのだが、最近になって、星野之宣の伝奇漫画『宗像教授』シリーズをゆっくり読み返す機会があって、やっぱり伝奇ものって面白いなあと思った。必要があって日本の神道や民間信仰の本を読む機会が続き、その複雑さを面白く感じていたのと、ここのところ、『ハリー・ポッター』や『ダ・ヴィンチ・コード』など、伝奇的なもの(ファンタジーは伝奇の一種だ)が世界的に流行るのも興味深く感じていたし。
読むジャンルとして大好きな伝奇小説と本格推理小説は、自分で書くには向いていないジャンルだと思っていた。自慢じゃないが、記憶力がないので資料が覚えられないし、論理的思考ができないことを重々自覚していたからだ。
しかし、ここ数年、伝奇小説も本格ミステリも、作り方は同じではないかと考えるようになってきた。言い方は悪いが、提示されている情報から好きなものを選んで好きな絵を描けばいい。沢山の点を打った紙があって、そのうち数字の付いている点を順番につないでいくと絵ができるのと同じで、同じように点を打った紙でも違う点を結べば違う絵が出来上がるのは当然。要はいかに綺麗な絵を描けるかなのだ。つまり、荒唐無稽な話やとんでもない話でも、線が全部つながっていてきちんとした絵になっていれば「お話」としてはいいのではないか、と。
そう考えるようになると、文庫の解説などでかつて読んだ小説の読み直しをするのが面白くなり、『夏の名残りの薔薇』という私が考える本格ミステリ(どこが本格なんだ! という声もあるが)が書けたので、じゃあ、やっぱり伝奇もやってみたいな、と思うようになったのだ。ただし、本格ミステリと違って伝奇小説は、選択すべき点の数が圧倒的に多いので、ひたすら点を増やしていかなければならないのが難点だけれど。
そんなわけで、点を増やすべく広く浅くいろいろな点を収集し続けているのだが、その途中で、ひとつの発見があったのだ。
自分では確かに伝奇モノが好きだとは思っていたが、そのルーツが今いちよく分からなかった。もちろん漫画に映画、小説にTVといろいろなものから影響を受けているのは確かだが、根っこの部分がぼんやりしていた。
去年、とあるエッセイの依頼があった。子供の頃に読んだ絵本から印象に残っている一冊について書く、という依頼で、私が何気なく選んだのがジョーダンの『ぺにろいやるのおにたいじ』という本だった。
好きな絵本、印象的な絵本といってもいろいろあって、絵が好きだったものとか雰囲気が好きだったものとか、一様には比べられないが、『ぺにろいやるのおにたいじ』は奇妙な内容が印象に残っていた。
ある国の王様のお城のそばに、恐ろしい鬼の住んでいる城があり、みんな鬼に怯えて生活している。征伐に行った者も、ことごとく追い返され、ひどい目に遭う。
ある日、「じゃあ僕が」とお城の家来の息子である小さな男の子が鬼を訪ねていく。
鬼は追い返そうとするが、「遊びましょう」とやってきた男の子が手に持っているのはおもちゃだけ。ぶちのめすわけにもいかず、渋々城に入れる。お城を案内しているうちに、鬼は人間の骨やら獣やらを見せるのが恥ずかしくて、どれも皆別のものに変えてしまう。人間の骨も麦わらにして、二人で遊び始めるとどんどんお城が小さくなってゆき、しまいには、お城の人が来てみたら、小さなテントの中で子供が二人夢中になって麦わら遊びをしていた、というもの。
当時は知らなかったが、ジョーダンはアメリカ人で、ヨーロッパからアメリカにやってきた移民に伝わる話を採録してこの絵本を書いたらしい。彼が生物学者で平和運動に従事していた、という経歴を知ると、このお話、いろいろ深読みができるのだが、それよりも私が気に掛かったのは、似たようにヨーロッパから北米に移民してきた人たちに伝わる話でやはりとても好きな本があったことを思い出したのだった。
『トンボソのおひめさま』という本だ。カナダに入植してきたヨーロッパ移民と先住民族の民話が混ざった話をこれまたバーボーとホーンヤンスキーという学者が採録した本らしい。いったい何回読んだか分からないくらい繰り返し読んだ本で、今も手に取ると必ず通して読んでしまう。
移民し、混血し、世代を経た人々のあいだに伝わる話を採録する。
そのような形を経て生き残ったお話には、当事者以外の学者肌の人が採集することもあって、失われたり、削ぎ落とされた部分もかなりあるだろう。逆に、そのことである種の客観性や寓話性を帯びてくる。話の核が強調されるか、あるいは同じくらい話の核心が隠蔽されてしまうことで、独特の雰囲気が産まれてくる。私はこの二冊の本に共通するその雰囲気に惹かれていたようなのだ。
美しい姫は突然部屋の中に現れたジャックに驚くが、ジャックの話を聞き、「私がそのベルトを身に着けても同じことができるのか?」と尋ねて「もちろん」と渡された魔法のベルトをせしめ、ジャックを叩き出してしまう。ジャックは国に帰って兄に財布を借りて買い戻そうとするがその財布も「私が使っても同じことができるのか?」と言われて姫に取られ、更にラッパを借りて兵隊で威嚇するが同じく「私が使っても同じことができるのか?」とラッパも取られてしまう。このジャックの学習能力のなさには呆れるが(こんなのが王子なのだからジリ貧の王国になってしまうわけだ)、何よりこの強欲な姫、しかもなかなかずる賢い姫が笑える。
さすがに三度目に叩きだされたジャックは深く反省する。国にも帰れず、ぼろぼろで水が飲みたいとたどりついた小川のほとりに、林檎とスモモの木があったので林檎を食べる。すると、鼻がどんどん長くなってしまい、仰天してスモモの実を食べると鼻が縮む。
そこで彼はこう叫ぶのだ。「ぼくはくだもの好きの誰かさんを知ってるぞ」
そう、実は最初にジャックが姫の部屋に現れた時、姫は林檎を齧っていたという伏線があるのである!
ジャックの逆襲開始。彼は物売りになりすまして林檎を売り、姫に林檎を食べさせることに成功する。そして、次に医者になってスモモを持って姫のところに現れるのだ。
そして、スモモと引き換えに三つの宝を取り返し、まだ鼻が縮み切らないうちに正体を明かし、「許してください。仲良くしましょう」としなを作る姫に「あんたみたいな鼻の長いお姫様、仲良くしたくないね」と言い捨てて、国に帰るのである。
この実に見事な構成、ほれぼれする。しかし、「トンボソ」ってどこ? 何語?
他の四つの話にも、古今東西「お話」のお約束とされるものがすべて入っている。
チャンスは三回。王子も三人。チャレンジに成功した男に与えられるのは美しいお姫様だ。魔女の館の開かずの間。もちろん、開けてしまい、馬に姿を変えられてしまった王子。または、魔女に追いかけられて、三つのものを投げつけるというのもお約束。
象に乗ったスルタンが登場するなど、どことなくイスラムの香りがするところも面白い。
考えてみれば至極当たり前のことなのだが、「不思議で珍しいお話」は、基本的に旅人や年寄りに「聞かせて」もらうものだったはずだ。ならば、心惹かれる話、あるいはエンターテインメントの原点はこの「人々に伝わる奇しい」お話である、つまり民話やメルヘンである、という全く当たり前のことに気付かされたのである。
そういえば、今年は『遠野物語』の初出版から百年目で、初めて『遠野物語』を読んだ時のわくわく感や面白さも『トンボソのおひめさま』に通じるものがあった。中でも山奥に無人のお屋敷があり、そこからお椀など什器のひとつを持ち帰ると金持ちになれる、という「マヨイガ」の話がとても好きだったのは、『トンボソのおひめさま』で、魔女の館のあかずの間の井戸に浸したものがみんな金になってしまう、という話が好きだったのと通低するのである。
これはやはり、どれだけかかっても、エンタメ作家のはしくれならば「伝奇もの」をひとつは書かねば、と決意を新たにしたのであった。
(2010.7.31)
