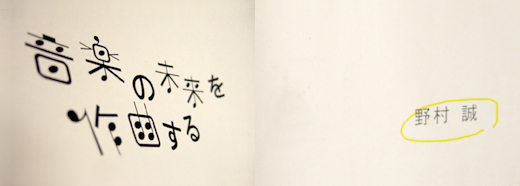
1 解けないナゾナゾを解く
子ども時代にバルトークに憧れ、現代音楽を志したぼくは、フィールドワークから音楽を創作する作曲家になった。バルトークは農村に出かけ民族音楽を収集したが、ぼくは、動物園、小学校、病院、老人ホームなどに出かけ、その時その場で、そこにいる人によって生み出される一回限りの音楽を体験してきた。こうした音楽は、別の場所で別の人が演奏しても、肝心の空気感が失われてしまう。また、その場でリアルに感じた雰囲気は、録音や映像には残らない。しかし、そんな奇跡的な音楽を一回限りに留めずに、その場にいない人ともシェアしたい、再体験したいと、ぼくは思う。持ち運びできない一回性こそ、生きた音楽の価値であり魅力であることは、十分承知の上で、その場限りの生きた音楽を再体験する方法を見つけたい、という矛盾した願望。その矛盾こそ、ぼくが作曲を続ける動機だ。だから、ぼくは即興音楽家としてではなく、あくまで作曲家と名乗り、この難問に挑み続けた。そうした試行錯誤の歴史が、「報告譜」、「ポスト・ワークショップ」、「考古学的な作曲」などの試みだった。
学生時代にバンドpou-fouで、「真似をしても似ない」、「個性は滲み出る」ということに気づいたように、過去の音楽を再現しようとしても、そこでは必ず「逸脱」という名の創造が起こってしまう。ぼくは、この逸脱を肯定的にとらえ、誤解、逸脱を推奨する「柔らかい楽譜」を探求した。「柔らかい楽譜」には、演奏の手続きだけでなく、浮かび上がった疑問も付記した。ぼくにとっての作曲は、音楽を完成させることではなくなり、音楽を成長させる仕組み作りになった。楽譜とは正解が用意されているマニュアルではなく、正解が無限に存在するナゾナゾ。いや、正解はそもそも存在しないのかもしれない。ぼくにとっての作曲は
音楽の中に、解けないナゾナゾを作ること
そのナゾナゾを作曲者のみで解くのではなく、他者と共同で解いていくこと
その際、個々の提案する解答の差異(=ずれ)こそを楽しむこと
そして、単なる「正解の用意されていない音楽」では物足りないので、解いてみたくなる「魅力ある謎」を含んだ音楽を追求した。そうした魅力を創出していくことこそ、作曲の醍醐味だと思った。「野村誠×北斎」では、北斎漫画に北斎が描いた尺八、琴、胡弓、木琴という四重奏を想像した。そこから想像される音楽は、謎めいていて、ぼくの興味を離さない魅力があった。たった一枚の絵が奏でる音楽を想像することで、全く違った曲想の10の音楽が生まれ、その後も、プロジェクトは継続し、10の楽曲は、さらに別の楽曲へと進化していった。
2 世界は音楽で満ち溢れている
作曲を始めた頃は、ジャンルを越境するなんて考えることもなかった。ただただ、純粋に音楽を追求していただけだった。ところが「しょうぎ作曲」を実践していくと、音楽の中に演劇やダンス的な要素が度々登場してきた。ぼくは、
音楽は演劇であり演劇は音楽である
音楽はダンスでありダンスは音楽である
と考え始めるようになった。そして、音楽と演劇が混在する遊び場、音楽とダンスが混在する遊び場で、数々の実験を行った。そして、様々な実験の末、演劇は音楽だし、ダンスだって音楽だと確信した。実際、幼児を観察すると、音楽とダンスと演劇が混在していることに気づく。そんな体験を経て、ぼくの音楽の定義は、音を聴くだけでなく、音を見る、音を触る、音を味わう、音を匂う、音を霊感する、という全感覚的な音体験になった。
作曲する遊び場で、ナンセンスな脱線を尊重していくと、どこまでも音楽の枠組みから逸脱していく。いたずら、動物の反応、雑音、冗談、ギャグ、音楽の外部に出るのではなく、どこまでいっても、魅力ある音楽だと感じた。ぼくにとっての音楽という概念が、どこまでも膨張し続けた。
では、何でも音楽なのだろうか?音楽になり得ないものはあるのだろうか?料理のレシピだって、壁紙の模様だって、心電図のグラフだって、空の雲だって、電話番号だって、幾何学だって、星空だって、地図だって、森だって、冷蔵庫の中だって‥‥、ぼくが、そこに音楽があると思った瞬間に、全部が音楽になってしまうのだ。そうか、世界は音楽に満ち溢れていて、「そこに音楽がある」とぼくが思えた瞬間に、音楽は存在するのだ。逆に言えば、そこには音楽がある、と思えない限りは、そこには音楽なんて存在しないのだ。ぼく自身の問題だったんだ。
楽器だってそうだ。ペットボトルは単なる容器だが、楽器だと思えた瞬間に素晴らしい楽器になる。石だって楽器だと思えた瞬間に、繊細な音色の打楽器になる。一方、ピアノが楽器だと知らなければ、ピアノは単なる黒くて大きな箱だ。
そうなると、ぼく自身がそう思えさえすれば、「全ての事象は楽譜」として見えてくることになるし、「全ての物は楽器」になる。ヴァイオリンを頂点とする楽器のヒエラルキーは崩壊して相対化される。竹輪とフルートと雨どいとペットボトルは等価になる。著名な指揮者を頂点とする音楽家のヒエラルキーもガラガラと崩れる。雨漏りの音と超絶技巧のギタリストが等価になる。全ては等価に音楽だ。相対化された広大な創造の海が広がっている。ぼくは呆然とする。ぼくは何を音楽にするのか?何を音楽にしないのか?ぼくは誰と音楽をするのか?誰と音楽をしないのか?葛飾北斎が見た物を片っ端から描いていったように、世界の全てを音楽にし続けていく作曲人生もある。しかし、限られた時間しかない人生で、全ての事象を音楽にするなんて不可能だ。ぼくは取捨選択を強いられる。
「芸術と社会包摂(ソーシャル・インクルージョン)」、「コミュニティとアート」などのキーワードを頻繁に耳にするようになり、「みんなのための芸術」をしなければいけない風潮に、ぼくらはしばしば曝される。「みんなが芸術家で、すべてが芸術である」と言ってしまう危険性。その瞬間に、全ての物が持っている価値が、等価に大暴落してしまい無価値になってしまうのではないか?全ての物が相対化されて、絶対的な価値が存在しない時代だからこそ、ぼくなりの価値を明確に発信したい。曖昧な「みんなのための音楽」をしている場合じゃない。最大公約数な音楽ではない。世界の全てが音楽で満ち溢れているからこそ、ぼくは明確に選択しよう。他の誰もが目を向けない微かな小さな音楽を。ぼくが心底愛せる音楽を。ぼくは、ドキュメンタリー・オペラ「復興ダンゴ」に取り組んだ。
3 復興ダンゴ
「復興ダンゴ」は、日本で大きな地震が起こった年に構想し、翌年に発表した。老人ホームのお年寄りから取材して作った作品だ。大震災は、津波や原発事故も誘発し、多くの命を奪い、不安と混乱を引き起こした。そして、様々な矛盾が次々に露呈し、そうした矛盾に対して、ほとんど何もできないでいる自分の無力感に愕然とした。自分が無力であることなど、百も承知だったけれども、そして、目先の結果ではなく、長期的な視野が重要だと、アートの文脈で何度も語られているのを聞いてきたけれども、それでも、津波の災害や原発事故を黙って傍観しているわけにはいかなかった。今という瞬間に何かアクションを起こしたいと強く願った。しかし、アクションを起こそうとすればするほど、自分の無力を知る。焦る気持ちを落ち着かせて、等身大の自分のできることから始めるしかないと悟れるまでに、どれだけの時間がかかったか。
世間では、「復興」という言葉が頻繁に使われていた。ぼくは違和感を感じていた。元に戻っていいのだろうか?災害によって露呈した問題点から目を背け、何事もなかったかのように元に戻ろうとしていないだろうか?そもそも、「復興」とは、どういう意味なの?そんな疑問から、「復興」をテーマにした作品を作ろうと、企画書を書き始めた。12年間通い続けている老人ホームに出向き、作品をつくることにした。お年寄り達に、太平洋戦争後の復興について語ってもらい、お話されるお年寄りの様子を映像や写真に収めて、そこから震災後の復興のヒントが浮かび上がるという構想だ。
世界は音楽に満たされているのだから、当然、お年寄りが復興について語る話は、音楽に満たされており、ダンスに満たされており、そこにはオペラがあるはずだ。そこには、震災後の復興のためのヒントが詰まっているはずだ。そう思って、取材に出かけた(コーディネートは吉野さつきさん、映像は上田謙太郎くん、写真は杉本文さんだった)。そして、お年寄りは戦後のことを90分ほど、話し続けてくれた。それはとても楽しい雑談だった。そこには、特筆すべき教訓もなく、発想の転換のヒントがあるようにも感じられず、ダンスや音楽に満たされている、とも感じない楽しい雑談だった。そして、ぼくが、そこに全てがあると信じなければ、これは、ダンスでも音楽でもオペラでもない単なるその場限りの雑談として、封印されてしまったと思う。
また、ぼくが自分の主張を語るためにドキュメンタリー作品を作りたいならば、何度も取材を繰り返し、ぼくが言って欲しいことをお年寄りが語ってくれるように誘導し、編集により、もっともらしくまとめることも可能だったろう。しかし、ぼくは、自分の主張を押しつけるためにオペラを作りたいのではなく、この90分の雑談の中で、お年寄りが意識的+無意識に語っていたメッセージを愚直なまでに、読み取りたいと思ったのだ。そこにこそ、音楽があり、ダンスがあり、復興のヒントがあるはずだと信じて。
これは、ぼくの勝手な思い込みと言ってもいいかもしれない。それでも、ぼくは、お年寄りの語りの抑揚の中にメロディーを探し、ダンスをお願いした砂連尾理さんは、お年寄りの微かな仕草の中にダンスを探した。すると、映像の中にも写真の中にも、その場にいた時には見過ごしていたような、非常に微かなメッセージの結晶が散りばめられていたのだ。世界は音楽で満ち溢れている。しかし、その多くは、非常に微かにメッセージで、見落とされ、忘れられてしまう。そうした小さな小さなメッセージ、場所や文脈を移してしまうと成立しないナイーブなメッセージ。そして、情報に溢れている世界の中で、権力も影響力もない小さなメッセージ。そうしたメッセージにこそ着眼し、そこから音楽を生み出し提示すること。それが、ぼくの選択だ。
4 ダジャレ
震災後に始めたもう一つのプロジェクト。それは、「ダジャレ」だった。原発事故後、友人は皆、口を揃えたように「原発はやめないといけない」と言った。会う人会う人、100%が反対していたので、日本国民のほぼ全員が反対していると錯覚した。しかし、どうもそうではないことが分かってきた。原発容認の人、推進の人、中間的な人、色々な人がいるらしいのだが、ぼくの周りには、そうした人が一人も現れてこないのだ。ぼくは、原発反対派の人ばかりと交流していて、原発賛成の人とは出会わない暮らしをしていたのだ。そして、ぼくは、原発に賛成する論理が全く理解できなかったし、賛成する気持ちを理解しようとしても、全く理解できなかった。理解できないから会って話をしてみたいと思っても、出会うことすらできなかった。同じ国の中にいながら、越えられない大きな壁で断絶されている向こう側の世界があるのだ、と思った。
これまで、ぼくは数々の壁を越えて、ジャンルを横断し、越境する活動をしてきたと思っていた。ライブハウス、コンサートホール、神社やお寺、動物園、老人ホーム、病院、大学、小学校、路上、テレビ番組、福祉フォーラム、ビール会社、美術館、博物館、銭湯、プールと、様々な場所で様々な人と交流をしながら音楽活動をしてきたつもりだった。でも、場所を変えても、結局のところ自分に似た考えの人とばかり交流してきたのかもしれない。原発反対の人ばかりで構成されている世界の向こうに、原発賛成の人ばかりで集まっている世界もあって、その間にある越えられない巨大な壁がイメージされた。
でも、賛成、反対と二極化した対立をしている場合じゃない。放射能被曝と共存を強いられている現状。この国土で生きていくために、対立している場合ではない。対立を越えて、交わらなければ。賛成の人も反対の人も交えて協力することこそ必要な非常事態ではないか。ぼくは悩み、そして、はっと気づいて唖然とした。交わっていないのは、ぼくの方ではないのか?壁を作っているのは、ぼくなのではないか、と。
権力や権威を無自覚に軽蔑して、拒絶していたのは、ぼくではないのか。権力や権威に流される大衆を、軽蔑していなかったか。そして、自分自身は、反体制や反権力の立場に安住していたのではないか。もっと、政治、経済に深く突っ込んで参加できたのに怠ってきたのではないのか?スーツやネクタイに象徴される世界を堅苦しいと感じ、自由を求めて活動していると言いながら、狭い芸術の世界に安住しているだけなのではないか?壁の向こうにある大多数のスーツやネクタイに象徴される世界に、ぼくの音楽は本当の意味で開いていたか?自分の周囲に似た思想の人ばかりが集まるのは、似た者同士の傷のなめ合いになっていたからではないのか?
ぼく自身が作っていたであろう壁を、少しずつ壊していくこと。それしかない。ぼくが築き上げた小さな実績やプライドなど、そんなものを少しずつ捨てて、勇気を持って一歩を踏み出すんだ。ぼくが勝手に作っていた壁の向こうの住人たちと、対話を始めるんだ。壁の向こうには、企業の歯車の中で身動きできず苦悩し奮闘するサラリーマンの姿が見えた。そして、何を彼らとシェアできるだろう、と考えた。「おやじギャグ」を連発し孤立し奮闘する「おじさん」と、ダジャレ談義をすれば、壁を越えられるのではないか、と思った。「だじゃれ」と「芸術」をつなぐプロジェクトで、自分の中に作っていた壁を越えようと決意し、「千住だじゃれ音楽祭」を立ち上げることにした。
5 ダジャレ作曲
実を言うと、「だじゃれ」の魅力を教えてくれたのは、若いアーティスト達からだった。かつて、ぼくが「取手アートプロジェクト」のゲスト・プロデューサーをした時、公募書類の中から選出したアーティスト達の中には、ダジャレからアート作品を作っている人が何人もいたのだ。山中カメラは、「オンド・マルトノ」というシンセサイザーの前進の電子楽器から駄洒落で着想し、「マルトノ音頭」という盆踊りを作った。「オンド・マルトノ」と盆踊りは、「オンド」という発音以外に全く無関係なのだが、無関係な2点が結ばれてしまうところが、駄洒落の凄いところだ。「腸々夫人」というタイトルの漫画を描いていた宮田篤とは、その後、「らくがっき」というプロジェクトをした。楽に楽器が描ける絵描き歌(さっきょく歌)をつくり、絵描き歌を解読する方法を考案した。
そんな彼らに影響を受けたのだろう。気がつくと、ぼくは「ダジャレ作曲」を考案した。世界は音楽で満ち溢れているのだから、あらゆる言葉は楽譜でもある。言葉を楽譜として解読しようと思った時、ダジャレの手法は非常に効果的だと気づいた。例えば、「福岡トリエンナーレ」という吹奏楽曲を作った時、「ふく」、「おか」、「とり」、「えん」、「な」、「あれ」とタイトルを分解し、ダジャレで発想した。「ふく」=楽器を吹く、「おか」=おかしな音を出す、「とり」=トリル、「えん」=楽器で円を描いて演奏、「な」=名前を演奏、「あれ」=あれ?という感じで終わる、とダジャレ的な発想で、演奏方法が次々に解読できた。また、「ソプラノ・バス」という曲は、「ソプ」と「ラノバス」に分解して、「ソープ」と「ラ伸ばす」と変形させて、石鹸を演奏し、ラの音を伸ばす曲にした。
こうした「ダジャレ作曲」で生まれた音楽は、とても新鮮だった。というのは、ダジャレで発想すると、論理的には全く無関係な物が並列されてしまい、意外な取り合わせが生まれるのだ。そう思った時、この方法に増々可能性を感じた。キーワード検索で膨大な情報を一気に絞り込むことができる現代、欲しい情報やその周縁のことに簡単に出会える反面、それとは無関係な情報を無駄に寄り道することが減ってきているように思う。その結果、似た思想の人がインターネット上で、密にコミュニケートできるし、違ったジャンルの異質な出会いが、どんどん減ってきてしまう。だからこそ、異界を結びつける装置としての「ダジャレ作曲」に、ぼくは魅力を感じているのだと思う。
2012.3.23 update
